WordPressは“実践の確認・保存”の場所。この記事は、練習の途中で 立ち止まり→確認→再開 するための短いマニュアルです。
あなたの悩み
-
ポーズをきれいに見せようとすると、呼吸が止まる。
-
形を作ってから呼吸を合わせると、窮屈で安定しない。
-
前屈・後屈・ねじりで、伸びは感じるが楽ではない。
結論:呼吸が止まった時点で、その形は崩れています。 呼吸に合わせて動くと、形は後から自然に整います。
誤解 vs 正解
| よくある誤解 | 実はこうする |
|---|---|
| 形を作ってから呼吸する | 呼吸に合わせて動く(呼吸が先、形は後) |
| 「丸める時に吐く」「反る時に吸う」 | 吐くから丸まる / 吸うから反る(順序を逆転) |
| “深呼吸しなきゃ”と気負う | 自分なりにスムースに通る呼吸を基準にする |
| 鼻呼吸が絶対 | 基本は鼻呼吸。ただし吐きづらい時は口から吐いてOK |
※ ネコのポーズはこの原則がもっとも体感しやすい

実践チェックリスト(マット横スクショ推奨)
-
☐ 吐く息に合わせて前屈できている
-
☐ 吸う息で胸がわずかに持ち上がる後屈になっている
-
☐ 吸う息で背を伸ばし、吐く息でねじる
-
☐ 呼吸が止まったらただちに強度を1段階ゆるめる
-
☐ “がんばっての深呼吸”より“自然に呼吸が通る状態”を優先する
※ここで紹介しているのは“基本の型”。
ただし、順番そのものが正解というわけではありません。
たとえば「吸って丸まる」「吐いて反る」でも、呼吸と動きがつながっていればOKです。
大切なのは“呼吸が止まらないこと”。 その一貫性さえあれば、動きと順序は自然に調整してかまいません。
基本練習(A→B→Cで基本的な動きを体感しよう)
「呼吸を意識せず伸ばす」VS「呼吸と合わせて動く」の違いを比べてみよう。
A|前屈(立位でも座位でもOK)
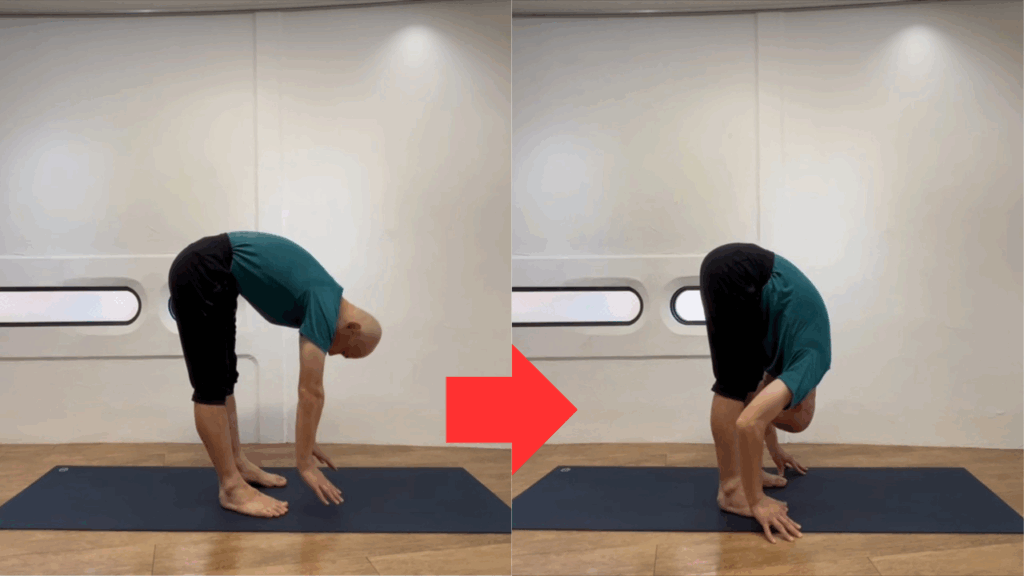
-
吐く息に合わせて前屈。肘・頭の重さを地面に落ちつかせる。
-
吸う息は今回は特に意識しない。ひと息つく感覚でよい。
-
5呼吸。呼吸が止まったら高さを上げる or 膝を緩める。
B|後屈(コブラのポーズ:ブジャンガーサナ)
-
吸う息に合わせて胸骨が前へ。両手は床を押すが、腰を詰めない。
-
吐く息で肩・顎の余分な力を抜く。
-
3〜5呼吸。痛みが出たら角度を即座に下げる。
C|ツイスト(座位のねじり)
-
吸う息で背を伸ばす(背骨や肋骨に空間ができる感覚)。
-
吐く息に合わせてねじる。1でできた空間分動かす。
-
5呼吸。首だけ先に回さない。下から(腰・背中→胸→首)順にひねる。
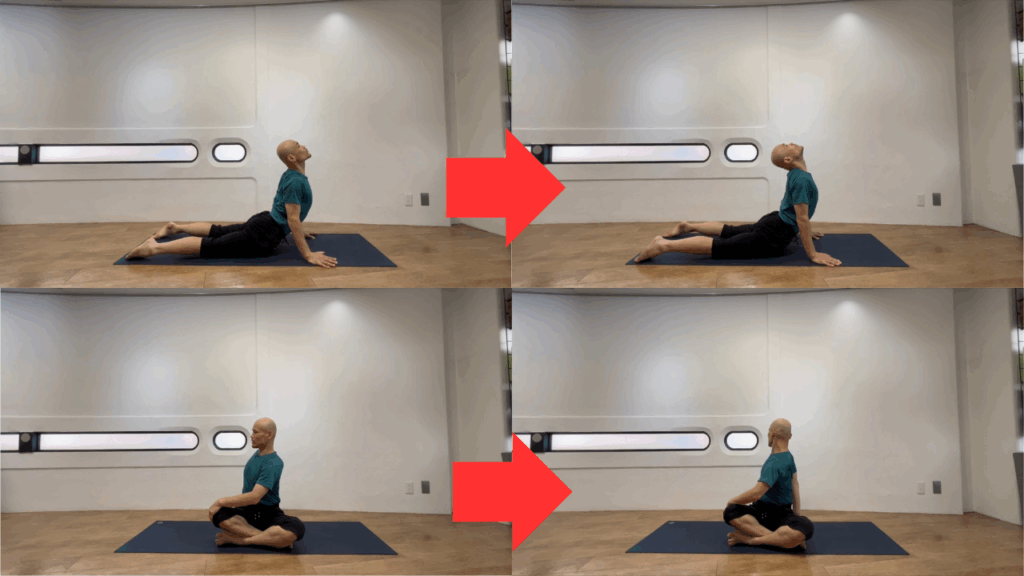
よくある失敗例(詰まるポイント)
-
形を先に決め、呼吸が後回しになっている
-
「丸まりながら吐く」──動きが先、呼吸が追いかけて分離
-
後屈で背骨の動きだけ意識(胸が広がらず、腰だけ反る)
-
ツイストで首ばかり回す(背中が伸びていない)
-
「深く吸おう」として力む(“長く、なめらかに”がコツ)
練習のヒントになる教え
ポーズは、呼吸が通って初めて安定する。 呼吸が止まっているポーズは、きれいに見えても未完成。
問い:今日、どの瞬間に呼吸が止まりましたか? 次に同じ場面が来たら、何を1つ緩めますか?
Q&A
Q1. 鼻呼吸が苦しいです。どうしたら?
A. 基本は鼻呼吸。ただし吐くのが苦しい時は口から吐いてOK。呼吸が通ることを優先。
Q2. 深呼吸が“深く”入りません。
A. “量”より長さ。たくさん吸うのではなく、細く長く吸う。背中側もふくらませるイメージで。
Q3. 形が崩れます。
A. 形は“結果”。呼吸に合わせて動くと、形は後から整います。止まったら強度を1段階下げる。
動画で“呼吸→動き”を体感する
▶ 再生チャプター
-
00:00|オープニング
-
00:17|今回の動画を見る前に前提として押さえておきたい呼吸の基本
-
01:57|呼吸と動きの関係の誤解について【ネコのポーズを通じて】
-
06:41|呼吸と動きを合わせるとポーズが深まるのを実感しよう【前屈編】
-
07:47|呼吸と動きを合わせるとポーズが深まるのを実感しよう【後屈編】
-
09:26|呼吸と動きを合わせるとポーズが深まるのを実感しよう【ツイスト編】
-
10:56|まとめ
関連記事
・📙保存版|ツイストの軸の作り方──背骨をひねらず“届ける”ねじり方【軸の誤解④】
※ 呼吸と同じく「動きの誤解」を解き直すシリーズ記事です。
・📗 note版|なぜ呼吸が大切か?──「形」や「力」よりも呼吸が安定を左右する
・📘 身体の使い方を、誤解から再教育する。──年間noteシリーズのご案内
あなたへの問い
-
さっきどの動きで呼吸が止まった?
-
止まったら、高さを上げる/膝を緩める/角度を1段下げる。どれを選ぶ?
-
次の1セット、“呼吸が通ること”を唯一の基準に動ける?
まとめ
呼吸が先、形は後。
「呼吸に合わせて動く」ことが大切であり、「動きに合わせて呼吸をする」のではありません。
──迷ったら、呼吸が通る体勢に戻すこと。それが“保存版の原則”です。