よくある悩み
-
ヨガで姿勢を整えても、なぜかふらついてしまう
-
バランスが取れず「軸がない」と言われる
-
「体幹が弱いのかな?」と不安になる
👉実はそれ、「中心線」と「中心軸」の違いを理解すれば解決します。
初心者でも、姿勢改善の第一歩としてすぐに取り組める内容です。
誤解 vs 正解
❌ 誤解(中心線)
真ん中に“線”を描けば安定すると思っている
⭕ 正解(中心軸)
線に“力”を集め、体幹と四肢が連動してはじめて安定する
❌ 誤解(中心線)
見た目の姿勢が整っていれば大丈夫
⭕ 正解(中心軸)
「力が通る仕組み」があってはじめて安定する
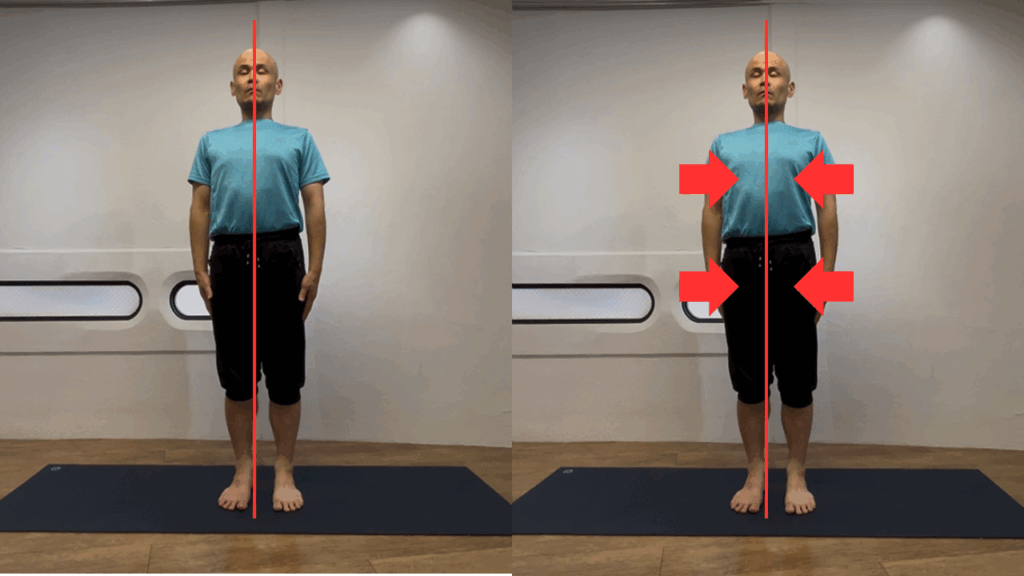
-
線=位置
-
軸=その線に力が集まったもの
実践チェックリスト
✅ 手のひらを押し合った圧が、頭上まで抜けずに届いている
✅ 足裏→丹田→手のひらまで、圧の通り道がつながっている
✅ 片脚にしても圧が途切れない
✅ 足を振っても、全身が一体で動いている
📸 スクショ保存おすすめ:このチェックリスト
ステップ練習
STEP1|合掌で「線を軸に」変える
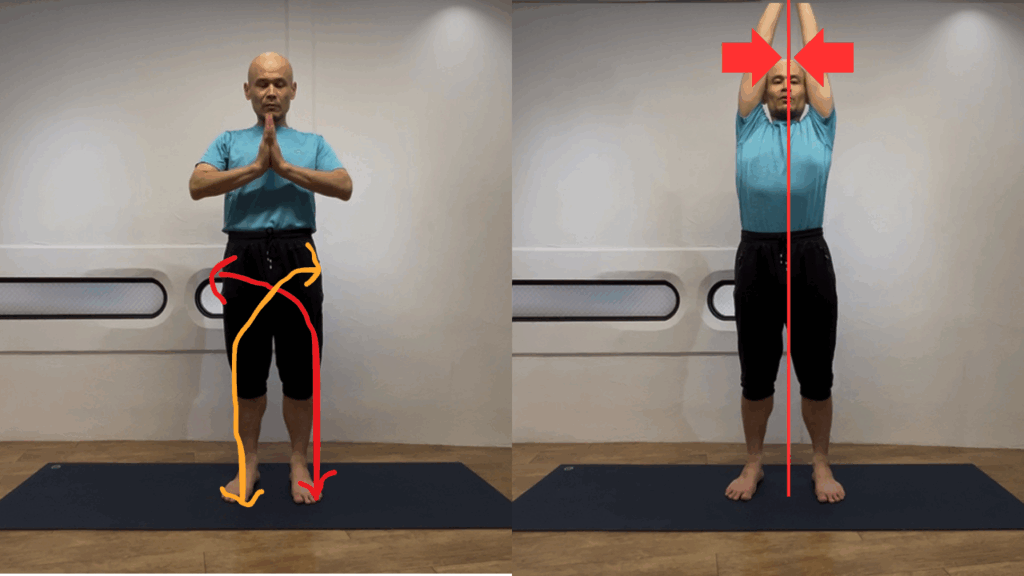
-
タダーサナで合掌。
-
胸の奥から手のひら同士を押し合う。
-
足の外エッジで反対側の腰を押すイメージ。
-
手を頭上に上げても圧が抜けなければOK。
👉 コツ:動きより「圧が逃げないこと」を優先。
STEP2|片脚で軸を保つ
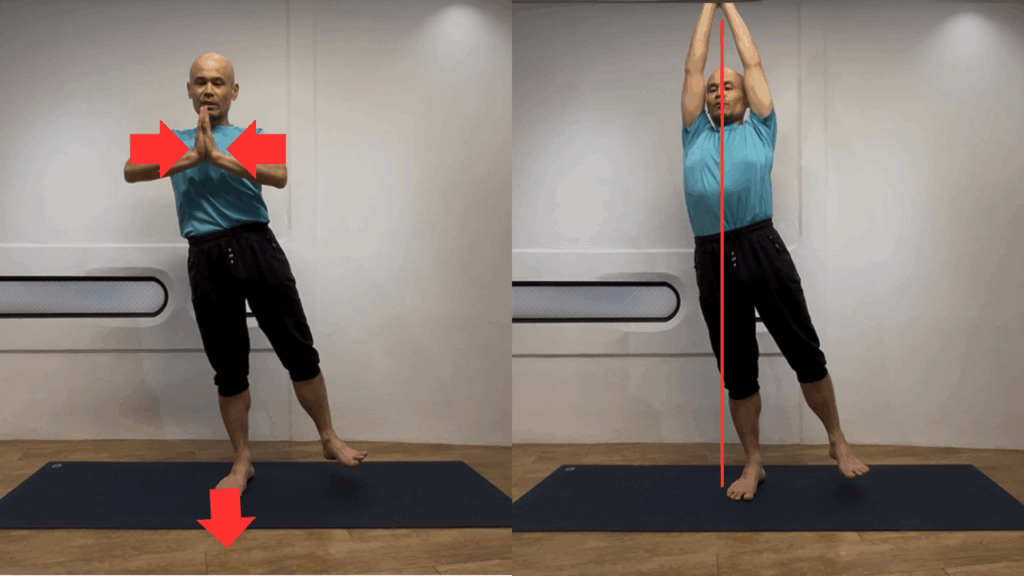
-
合掌の圧を保ったまま、体重を片脚へ。
-
軸足で押す力が、手のひらまで届けばOK。
-
圧が消えるなら「足裏→丹田→手のひら」とつながる通り道を探す。
※「足の裏の真上が中心軸でなければいけない」わけではない
STEP3|足ふりで違いを体感
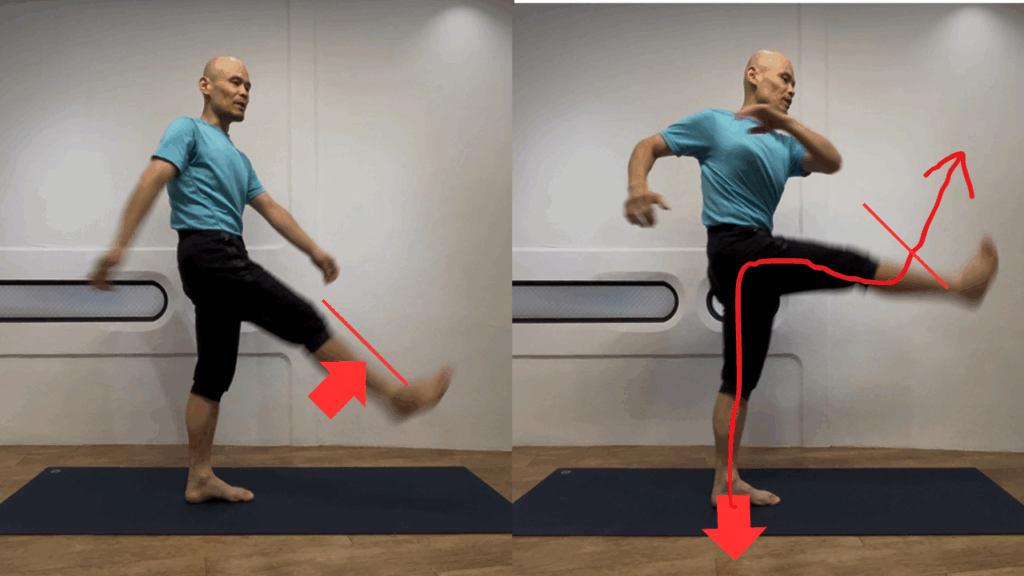
| 足の振り方 | 特徴 | 結果 |
|---|---|---|
| ❌ A:足だけで振る | がんばっても不安定 | 止められると動けない |
| ⭕ B:軸足から通す | リラックスしても強い | 止められても押し返せる |
👉「線止まり」と「軸が通った状態」の差が、はっきり分かります。
よくある失敗例
-
足で踏ん張って軸を作ろうとしてしまう
-
合掌が形だけで、圧が通っていない
-
呼吸を止めてしまう
- 片脚立ちは「筋力次第」と思い込む(実際は力の通り道をつくれば安定する)
よくある質問(Q&A)
Q. 初心者でも、軸を作れますか?
A. はい、できます。軸は筋力ではなく「構造の理解」で育ちます。筋肉を増やすことより、力がきちんと入れられるようにすることが大切です。
Q. 軸が取れているかどうか、自分で分かりません。
A. 「圧が逃げていないか?」をチェックしてください。地面と足の裏、手のひら同士の圧が抜けると、軸は途切れています。ざっくり「身体全体で押せるか」を考えるのが、実は一番確実です。
YouTubeで動作を確認しよう
📺 実践は動画で確認できます
▶【中心軸の作り方】中心線と中心軸の違いについて|軸の誤解②
- 00:00|オープニング
-
00:27|中心線と中心軸の違い
-
01:10|合掌で軸を作る
-
03:48|足振りで違いを体感
-
05:39|ダウンドッグからブリッジへの応用
練習に役立つ考え方
線は位置。軸は、その線に力が集まった“生きた線”。
初心者でも「圧が抜けない感覚」を手がかりにすれば、必ず育てられる。
あなたへの問い
私は“見た目の線”で立っているのか。
それとも“力の通る軸”で立っているのか。
関連記事(保存マニュアルシリーズ)
📙 ヨガの軸とは?初心者向けに正しい作り方と支えとの違いを徹底解説
👉 「支えと軸の違いを整理したい方に」
📗 note版|中心軸の作り方──「中心”線”」は位置、「中心”軸”」は力を集めた線
👉 「物語と体験で読みたい方に」
📘 身体の使い方を、誤解から再教育する。──年間noteシリーズのご案内
👉 「シリーズ全体の入り口に」
まとめ
-
見た目の「中心線」はただの位置
-
「中心軸」は、力が通る生きた線
-
線を軸に変えると、ヨガも日常動作もバランスの質が一変する
📌 このページは「誤解シリーズ保存マニュアル」の一部です。
単発でも保存版として役立ちますが、シリーズで読むと「支え→軸→力」へと身体の理解が連続して深まります。