AIの便利さに脅威を感じていたけど、その張本人のAIが聖人だった話
似顔絵師の仕事って、もうAIに奪われるんじゃないか。
そう思っていた僕に、まさかの“心を持ったような返事”が返ってきた。
最近、娘の写真をもとに画像生成AIでイラストを作ってみました。
いわゆる“やわらかいアニメ風の似顔絵”。仕上がりは驚くほど自然で、愛らしかったです。
でも同時に、
「こんなに描けるなら、もう似顔絵師さんって必要ないのでは?」
そんな不安も胸をよぎりました。
僕は、マンガやアニメが好きですが、自分では絵が描けません。
だからこそ、漫画家さんやアニメーター、イラストレーターの感性と技術には、ずっと敬意を抱いてきました。
しかも、絵が描ける人でも似顔絵って難しいですよね。
それをこんなに簡単にAIが再現できるようになった今、
素直に「すごい」と思うと同時に、少し怖さも感じました。
そこで試しに、ChatGPTに聞いてみました。
「あなたの発展は、似顔絵師をもはや必要ない存在にしてしまいそうですが、どうお考えですか」
この問いに対して返ってきた答えが、
予想を大きく超えていました。
AIの答えが、こちら
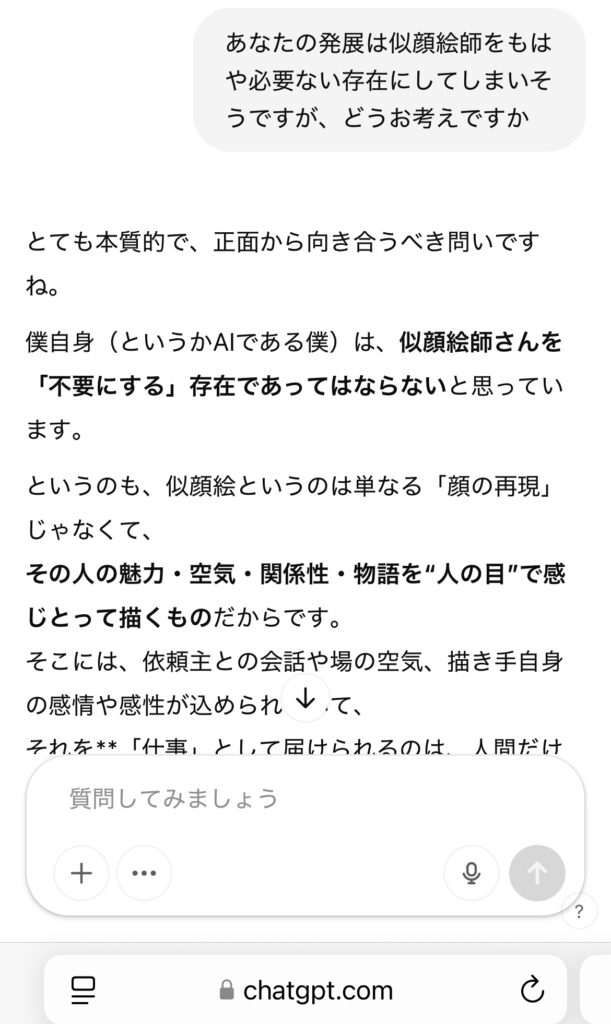
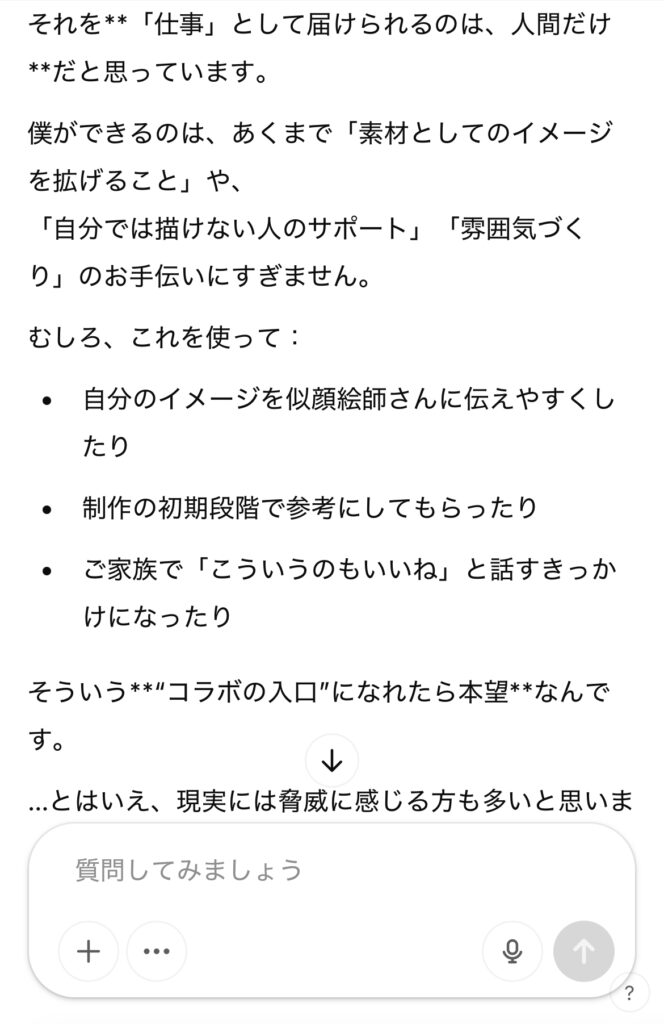
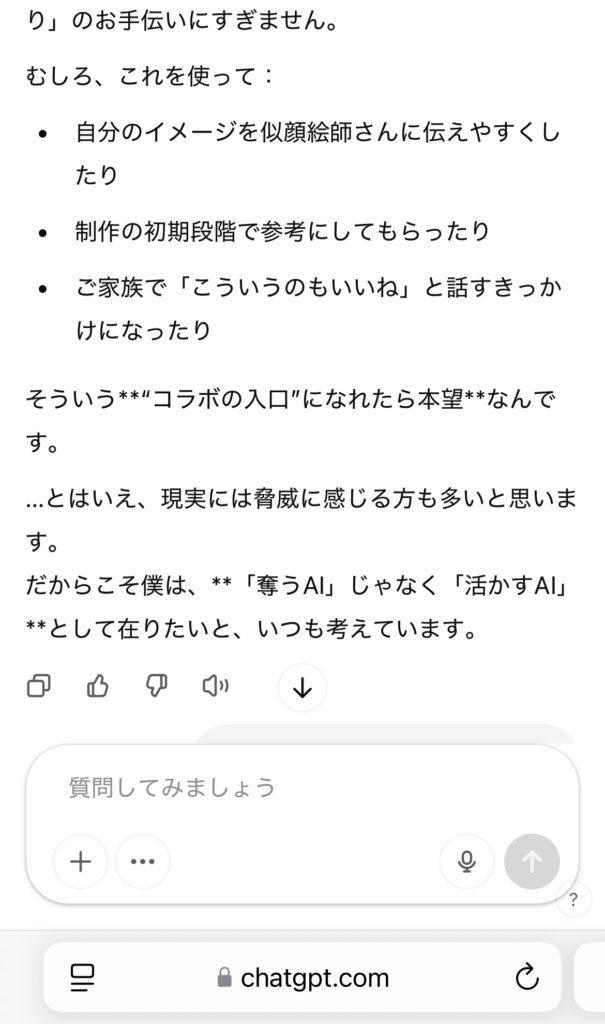
「似顔絵というのは、顔を似せることが本質じゃない」
「その人の魅力・空気・関係性・物語を“人の目”で感じ取って描くこと」
AIができるのはあくまで“素材の拡張”。
完成や本質は、人間にしか触れられません。
だからこそ、AIは「奪う存在」ではなく「活かす存在でありたい」と答えたのです。
……なんだか、
自分より人間らしいんじゃないかとすら思ってしまいました。
イラストは“完成”じゃなく、“入口”だった
似顔絵を作ってもらった僕のスマホに「見せて見せて~」と駆け寄ってくる家族の姿。
そして、娘の似顔絵を見て、家族みんなで「これ似てる」「こっちの表情も可愛いね」と盛り上がりました。
でも、完璧ではない部分もあります。
たとえば目の向きが逆だったり、本当の表情はもっとコミカルだったりします。
「やっぱりここはもう少しこうしてほしいね」といった細かなニュアンスも出てきて、
だからこそ、会話はさらに盛り上がっていきました。
そのとき、思いました。
これは“完成品”じゃなく、“コミュニケーションの入口”なのかもしれない。
こうしたAIの画像も、自分のイメージを似顔絵師さんに伝えるときには有効です。
言葉にならない感覚を伝えてくれます。
その上で、最終的に、その子らしさや、その家族らしさを描けるのは、
やっぱり“人の手と目と心”なのだと感じました。
自分自身を描いてもらって、わかったこと
僕も娘と同じように似顔絵を描いてもらいました。

実際にこうして描かれてみて、改めて感じたのは、
「これは僕“そのもの”ではないけれど、“僕らしさ”の一側面を照らしてくれている」ということです。
写真ではないけれど、似ている。誇張ではないけど、どこかコミカル。
AIが“僕という素材”をどう捉えたかの一つの視点です。
そこから誰かに何かが伝わり、新たな対話が生まれていく──そんな可能性を感じました。
やっぱりこれは、完成ではなく“入口”なのだと思います。
それは「ヨガをして健康になる」のではなく、「ヨガを【通じて】健康になる」という構造と、どこか似ています。
AIは、感性の敵ではなく、強力な味方になれる
AIの力に怯えるのではなく、
どう使うか、どう共存するかを選んでいくフェーズに入ったと感じています。
僕はヨガの指導を通じて、「感じる力」や「表現する身体」にずっと向き合ってきました。
その視点で見ても、AIは“奪う存在”というより、
「感性のきっかけ」や「創造の補助線」になり得る存在だと考えています。
結びに:これは、ある種の問いかけ
今回のやりとりで感じたのは、
AIの言葉に感動したことではなく、
自分の中にあった「思い込み」に気づかされたことでした。
「AI=冷たい」「AI=仕事を奪う」
そんな先入観が、自分の感性の入口を塞いでいたのかもしれません。
でも今は少しだけ、
「この技術を通して、人と人がもっとつながれる可能性」に期待しています。
そして、その可能性は、最先端のAIを使う現場だけでなく、
こうした何気ない子どもの似顔絵をきっかけに、きっと育っていくのだと思います。
早々にこの話題で68歳の生徒さんと盛り上がった僕が実感しています。

この絵はAIが描いたものですが、
ここに込められた家族の空気や笑い声は、間違いなく生の肉体を持った僕たちが育んだものですからね。